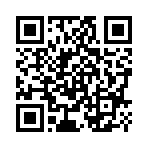2018年01月09日
非認知能力と認知能力

それでは非認知能力って? 認知能力って?をテーマに書いてみたいと思います。
認知能力とは・・・
☆文字がかける ☆数字が100まで言える ☆足し算ができる ☆英語が話せるetc...
これらは「認知能力」と言われます。
非認知能力とは・・・
☆感情のコントロール ☆自己解決能力 ☆考える力 ☆我慢する力 ☆諦めない心 ☆コミュニケーション能力 ☆感性etc....
目標に向かって頑張る力、他の人とうまく関わる力、感情をコントロールする力などです。
数がわかる、字が書けるなど、IQなどで測れる力を「認知的能力」と呼ぶ一方で、
IQなどで測れない内面(心)の力のことを「非認知的能力」と呼んでいます。
いま、日本でも注目されていることの一つで、2017年3月から保育園(幼稚園・こども園)、小学校、中学校、高校で共通のテーマとして組み込まれました。
それは、将来大人になってから、自分で考えられる力、困難(問題)に向き合い乗り越える力、仲間と協力する力などを身につけて、人生を歩んでほしいという想いがあるということです。

なぜ非認知能力が大切なの?
白梅大学の教授である、汐見稔幸さんはこう解説しています。
「私たちは『文字が読める、うまくブロックを積み上げられる、三角形と四角形と五角形を区別できる』といった、目に見えて知的に賢くなったと感じる認知的な能力を重視しがちです。
しかし、幼児期に認知的な能力を高めることが、その後の人生の成功や安定につながっているのか、いろいろ調べた結果、あまり関係がないことがわかってきました。
大事なことは、うまくいかないときに諦めず『どうしてかな』『こうやってみよう』『これがだめなら、ああやってみよう』など、あくまで目標の達成まで頑張る姿勢を身につけることです。我慢できること、感情をコントロールする力なども大事です。
そのような力は一生残ります。大人になって社会で成功する力につながります。」
「どちらが良い・悪い」という話ではなく、どちらも大切な能力です(*^^*)
ただ、非認知能力は幼少期に獲得しやすい。
また、非認知能力の器ができていると認知能力の伸びもぐーん!と、より良くなるということなんですねぇ~
乳幼児期の素直なうちに、非認知能力を十分に高めてあげられるような働きかけをして、認知能力を受けとめられる器作りをしていきたいと私たちは考えています。
次の記事ではこどもたちのやり取り中で見つけた非認知能力のエピソードをご紹介しますね♡
Posted by kazeuta at 16:07│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。