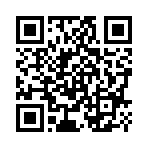2018年11月12日
待ちに待ったピクニック兼運動会は楽しかったです。
先日(10月27日・土曜日)に、もう20年以上も前から続けている「ピクニック兼うんどう会」を行いました。
風のうたの運動会は“風の奏でるうたが聴こえますか?”
と題して青空の下、森林公園で行っています。
森林浴でエネルギーを入れ替えて(深呼吸)大人もリラックスできるな~と思っているからです。
リハーサル風景(小さいクラスさんが憧れのまなざしを送っています)

芝生なので、太陽の照り返しはないし、森林公園なので音は木々が吸収して子どもたちの声は心地よく癒されます。
でも那覇市内にあるので、近隣の住宅の方へはご迷惑をおかけしていますが、年一回の運動会をやれている感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。m(__)m


運動会は、その時期の子どもの「運動面の発達」をみていただく行事です。
例えば「走る」ことにおける発達は
0.1歳児の「寝返り」→「ずり這い」→「ハイハイ」→「つたい歩き」→「よちよち歩き」と次第に発達していき、2歳児になったらもう立派に「走る」となります。走るのも「まっすぐ走る」「手を振って走る」とだんだん進んでいき、5歳児の年長ともなればリレーをし「協力して走る」という形になってきます。
発育発達の進み方は、男女の違い、年齢の違い、個人差が見られます。また、運動経験の差による違いも関係するといわれています。一人ひとりの個人差を考えながら日々、望ましい方法や援助を模索しています。
朝の登園一つとっても、「抱っこ」での登園の子、毎朝15分の道のりを歩いて登園する子の運動面の発達は、大きく異なります。また、静かに遊ぶのが好きな子と、公園等で体を動かすことが大好きな子とも筋肉や随意筋の発達は異なります。
運動会では、ふだんの遊びの中で身に着けた「運動面の発達」を「今、この子の発達はどれくらいかな」という目線でも、楽しんでほしいと思います。(各クラスの運動会演目紹介を配布いたしました)


日々、子どもたちと過ごしていると“やりた~い”という想いがあふれ出ているなぁと感じます。
子どもたちの“やりた~い”が一人一人の夢につなげられるよう向き合い続けています。
すると、大人が満足する「完成度(やらせる)」に偏らず、「こども一人一人が自分の感覚で、一体感も感じながら楽しむ(発達に合った動きをする)」という行事のあり方を大切にしていくようになりました。
子ども自身の“開放感”“ゆったり感”“お母さん(お父さん)と共に居る”という喜び感が根底にあり、“お友達と一緒にやることが楽しい”という想いが湧き出ている・・・それをみて大人も満足する・・・いいですねぇ~


たまに「いやだぁ~」と言って大泣きする子や「遊びたい」とママから離れない子がいます。
「一緒に出よう♪~」と促すことはいたしますが、無理強いはしません。
最終的に「出るか、出ないか」の選択は子ども自身に決めてもらっています。(これまでの経験では、ずーと「出ない」を選択する子は一人もいませんでしたよ。「次」がいつどぁるか?は個人差はありますが、自ら進んで参加する姿を必ず見せてくれます)


今回もリハーサルや練習の時、「いやだ!!」と言ってた男の子が、全種目張り切って参加してましたよ。
(実際リハーサルでやらない選択をしていても「リハーサル」という環境には身を置いていたので、本場にはやれたと思います。ここが子どものすごいところでだと思っています^0^)
・「運動会に積極的に参加する」
・「輪の外側で遠慮がちに参加する子」
・「輪にまったく入らずピクニックだけを楽しんでいる子」
・「お母さんやお父さんに抱きついている子」
子どもたちは、様々な「自分」を表現します。
のびのびと、ゆったりと、楽しい歓声で(泣く子はいるけれど)「運動会への無理強いで泣いている声」は聴こえない・・素敵な空間でした。


この幼い頃に「運動会って楽しい、嬉しい」と子ども自身が感じることが、小学校へ進学して「頑張り」や「達成感」につながり、「楽しい嬉しい運動会本番」に向けて“暑い中での練習”を“喜び”に変えられるのではないかなぁと思います。
全員が運動会って楽しいと感じることは全員が自分の一番気持ちいい状態でそこに居るということです。ナンバーワンでなくてもいいオンリーワンなんですもの。子どもたちを大きなサイクルの中で、長いスパン(期間)の中で小学生・中学生になっても「運動会大好き」な子どもへと成長してほしいと思っています。
だから、いろいろな「楽しい」の表現があってもいいかな?いろいろな「楽しい」の場があってもいいかな?と思います。(小中学生になっている卒園生を見ていると頼もしく思います。)


子ども本人の気持ちの上になりたつ行事ですので「笛(号令笛)」は要りません。強制は無しです。
ただし、集団としてのルールはありますので、言葉やお歌で伝えながら集団の大切さも学んでもらえると思います(社会性の発達)
パパママそして私たち、大人としてのモラルも子どもたちに試される時間です(笑)
昨年は雨で、体育館でやりました。それはそれで楽しかったですが、やはり森林公園はいいですね~
お弁当の時間は、ジブリ美術館で上映している「星を買った日」のサウンドトラックを流しています。
う~ん最高の空間でした。
こどもたちありがとう

風のうたの運動会は“風の奏でるうたが聴こえますか?”
と題して青空の下、森林公園で行っています。
森林浴でエネルギーを入れ替えて(深呼吸)大人もリラックスできるな~と思っているからです。
リハーサル風景(小さいクラスさんが憧れのまなざしを送っています)

芝生なので、太陽の照り返しはないし、森林公園なので音は木々が吸収して子どもたちの声は心地よく癒されます。
でも那覇市内にあるので、近隣の住宅の方へはご迷惑をおかけしていますが、年一回の運動会をやれている感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。m(__)m
(0歳児クラスの様子)
運動会は、その時期の子どもの「運動面の発達」をみていただく行事です。
例えば「走る」ことにおける発達は
0.1歳児の「寝返り」→「ずり這い」→「ハイハイ」→「つたい歩き」→「よちよち歩き」と次第に発達していき、2歳児になったらもう立派に「走る」となります。走るのも「まっすぐ走る」「手を振って走る」とだんだん進んでいき、5歳児の年長ともなればリレーをし「協力して走る」という形になってきます。
発育発達の進み方は、男女の違い、年齢の違い、個人差が見られます。また、運動経験の差による違いも関係するといわれています。一人ひとりの個人差を考えながら日々、望ましい方法や援助を模索しています。
朝の登園一つとっても、「抱っこ」での登園の子、毎朝15分の道のりを歩いて登園する子の運動面の発達は、大きく異なります。また、静かに遊ぶのが好きな子と、公園等で体を動かすことが大好きな子とも筋肉や随意筋の発達は異なります。
運動会では、ふだんの遊びの中で身に着けた「運動面の発達」を「今、この子の発達はどれくらいかな」という目線でも、楽しんでほしいと思います。(各クラスの運動会演目紹介を配布いたしました)
(1歳児クラスの様子)
日々、子どもたちと過ごしていると“やりた~い”という想いがあふれ出ているなぁと感じます。
子どもたちの“やりた~い”が一人一人の夢につなげられるよう向き合い続けています。
すると、大人が満足する「完成度(やらせる)」に偏らず、「こども一人一人が自分の感覚で、一体感も感じながら楽しむ(発達に合った動きをする)」という行事のあり方を大切にしていくようになりました。
子ども自身の“開放感”“ゆったり感”“お母さん(お父さん)と共に居る”という喜び感が根底にあり、“お友達と一緒にやることが楽しい”という想いが湧き出ている・・・それをみて大人も満足する・・・いいですねぇ~
(2歳児クラスの様子)
たまに「いやだぁ~」と言って大泣きする子や「遊びたい」とママから離れない子がいます。
「一緒に出よう♪~」と促すことはいたしますが、無理強いはしません。
最終的に「出るか、出ないか」の選択は子ども自身に決めてもらっています。(これまでの経験では、ずーと「出ない」を選択する子は一人もいませんでしたよ。「次」がいつどぁるか?は個人差はありますが、自ら進んで参加する姿を必ず見せてくれます)
(3歳児クラスの様子)
今回もリハーサルや練習の時、「いやだ!!」と言ってた男の子が、全種目張り切って参加してましたよ。
(実際リハーサルでやらない選択をしていても「リハーサル」という環境には身を置いていたので、本場にはやれたと思います。ここが子どものすごいところでだと思っています^0^)
・「運動会に積極的に参加する」
・「輪の外側で遠慮がちに参加する子」
・「輪にまったく入らずピクニックだけを楽しんでいる子」
・「お母さんやお父さんに抱きついている子」
子どもたちは、様々な「自分」を表現します。
のびのびと、ゆったりと、楽しい歓声で(泣く子はいるけれど)「運動会への無理強いで泣いている声」は聴こえない・・素敵な空間でした。
(4歳児クラスの様子)
この幼い頃に「運動会って楽しい、嬉しい」と子ども自身が感じることが、小学校へ進学して「頑張り」や「達成感」につながり、「楽しい嬉しい運動会本番」に向けて“暑い中での練習”を“喜び”に変えられるのではないかなぁと思います。
全員が運動会って楽しいと感じることは全員が自分の一番気持ちいい状態でそこに居るということです。ナンバーワンでなくてもいいオンリーワンなんですもの。子どもたちを大きなサイクルの中で、長いスパン(期間)の中で小学生・中学生になっても「運動会大好き」な子どもへと成長してほしいと思っています。
だから、いろいろな「楽しい」の表現があってもいいかな?いろいろな「楽しい」の場があってもいいかな?と思います。(小中学生になっている卒園生を見ていると頼もしく思います。)
(5歳児クラスの様子)
子ども本人の気持ちの上になりたつ行事ですので「笛(号令笛)」は要りません。強制は無しです。
ただし、集団としてのルールはありますので、言葉やお歌で伝えながら集団の大切さも学んでもらえると思います(社会性の発達)
パパママそして私たち、大人としてのモラルも子どもたちに試される時間です(笑)
昨年は雨で、体育館でやりました。それはそれで楽しかったですが、やはり森林公園はいいですね~
お弁当の時間は、ジブリ美術館で上映している「星を買った日」のサウンドトラックを流しています。
う~ん最高の空間でした。
こどもたちありがとう
Posted by kazeuta at 14:11│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。